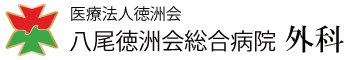国境なき医師団(Médecins Sans Frontières=MSF)は、民間で非営利の医療・人道援助団体です。紛争や自然災害、貧困などにより危機に直面する人びとに、独立・中立・公平な立場で緊急医療援助を届けています。1971年にフランスで設立され、1999年には活動の実績が認められノーベル平和賞を受賞しました。私は高校生の時、このニュースを見て医師になることを決めました。難民キャンプで赤ちゃんを抱える虚ろな目をした黒人女性の姿が、今も鮮明に記憶に焼き付いています。
これまでにも、ミャンマー、パキスタン、イラク、南スーダンなど、中東、アジア、アフリカの紛争地域での援助活動に参加してきました。危険な地域に、各専門領域の外国人医師を送り込むことはできないため、外科医に求められる技術は非常に多岐にわたります。私の専門である一般的な腹部の手術に加え、やけどに対する植皮、骨折の手術、銃や爆弾による外傷、帝王切開、さらには開頭手術まで求められることもあります。しかし日本では銃や爆弾による外傷に触れる機会はほとんどなく、やけどは形成外科、骨折は整形外科、出産は産科と言うふうに診療科が分かれており、MSFの現場で必要とされる総合的な外科経験を積むことは困難です。日本人外科医がMSFに派遣されるハードルの高さの一因でもあります。
南アフリカは紛争地域ではありませんが、非常に治安が悪い国で、銃やナイフによる外傷が多数発生しています。今回、私は外傷手術のさらなる技術向上を目指し、5月から6月の2ヶ月間、南アフリカ共和国ケープタウンにあるTygerberg Hospitalに派遣されました。


この病院は、人口300万人をカバーするレベル1の外傷センターで、1日あたり平均30~60人の外傷患者が搬送されてきます。特に目立つのが銃創や刺創による若年層の重症例で、暴力が日常の一部となっている社会の現実に大きな衝撃を受けました。この現状の背景には、南アフリカが経験してきた「アパルトヘイト(人種隔離政策)」の長い歴史があります。
1994年、ネルソン・マンデラ氏が南アフリカ初の黒人大統領に選ばれ、法的には隔離政策は終わりを迎えました。マンデラ氏はその功績により1993年、ノーベル平和賞を受賞しています。彼が目指したのは、人種や文化の違いを尊重し共存する多民族国家。彼はその理想を「虹の国(Rainbow Nation)」と呼びました。虹のように多様性が共に輝く社会。しかしその理想は、いまだ道半ばです。郊外には「タウンシップ」と呼ばれる黒人貧困層の居住区が広がり、失業率や犯罪率は高く、暴力が連鎖しています。私は連日、銃弾に倒れた少年や、ギャングの抗争に巻き込まれた青年の手術を行いながら、医療だけではどうにもならない現実を感じました。
Tygerberg Hospitalでは、看護師たちは“シスター”と呼ばれており、手術が終わると「Let’s dance!」と言いながら音楽に合わせて踊るなど、明るく前向きな雰囲気が印象的でした。また、現地医師たちも、飛行機で20時間以上もかかる東アジアから来た日本人を外傷チームの一員として迎え入れてくれました。

危険な地域もありますが、ケープタウンにはたくさんの観光名所もあり、休日にはアフリカ大陸最南西端の喜望峰や、ビーチでペンギンが見れるペンギンビーチにも行けました。ケープタウンは世界的にもいい波が立つことで有名な場所で、一日だけですが、私の趣味である、サーフィンにも行くこともできました。大自然に癒された時間もいい思い出になりました。


私たち日本人は、幸運にも世界一平和な国で生まれて生活しています。けれどもし、わずかに時間と空間が違えば、紛争や飢え、貧困、暴力にさらされていたかもしれません。現在も、ウクライナやガザでは紛争が起きていますし、各地で自然災害も発生しています。現地に行くことができなくても、無関心にならず、命の危機に瀕する人々に思いを馳せ、胸を痛めるだけでも救いになると思います。報道では悪いことばかり報道され、悪いニュースは広まりやすいため、世界はどんどん悪くなっていると錯覚しがちですが、実際には良くなっていることもたくさんあります。乳幼児死亡率や極度の貧困で暮らす人々、災害で亡くなる人は減っていますし、安全な飲料水を確保できる人、予防接種を受けることができる子供も増えています。いつか、紛争や災害、貧困で私のような外科医を必要とする人々が世界中からいなくなる日が来ることを願いながらも、いつでも派遣される準備をして、日々自分の知識と技術を向上させています。今回このような貴重な機会をいただいたことに感謝するとともに、現地で出会った全ての患者さん、スタッフの皆さんに心から感謝申し上げます。